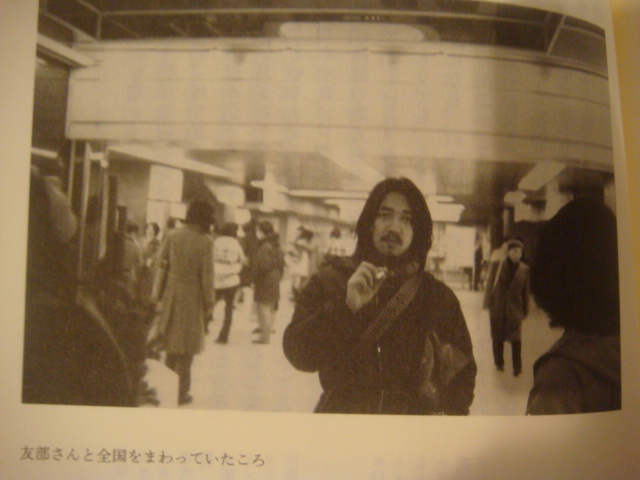久々のヨーロッパ、オーストリア(ウィーン)に行ってきた。
2014年にスペイン(バルセロナ)に行っているので、久々というわけでもないのだけど、久々という感じがしたのは夏にも関わらず肌寒かったからだと思う。
僕が最初に行った海外はフランス。確か24歳くらいだった。当時、近代〜現代美術にかぶれていたので、パリの美術館をひたすらハシゴした。その時は冬で空はどんより曇っていた。その後、イギリスやイタリア、そしてまたフランスと、何度か行ったけれど、夏に行ったとしても大体寒くて曇っていた。「寒くて曇っている」。これが僕のヨーロッパへの、偏見に満ちた印象である。
一昨年に行ったスペインは珍しく晴れて暑かったので、この印象にカウントされていない。すごく不思議なのだけど、僕としてはあまりヨーロッパという感じがしなかった。あらためて最初に受けた印象というのは本当にすごいなと思う。

ウィーンというとなんとなく金ぴかで、モーツァルトで、食べ物がフライで、甘いものが多そうで、という印象しかなかったけど、それは大体合っていた。
要はもともとハプスブルク家という、とんでもなく長い歴史を持つ一族の帝都であり、20世紀初頭の帝政崩壊後も特に侵略もされず、チェコのように社会主義に飲まれることもなく、永世中立国としてそのまままったりと今に至る街なので、王政時代の名残がそこかしこにある、というだけのことである。
政治的な衝突や軋轢、芸術的な反動といったものは少なからずあったのかもしれないが、オルタナティブとか、ヒップとか、あるいはニューエイジだとか、そういう感覚から遠い街であることは確かだ。
ヨーロッパの歴史に疎く、観光も甘いものも苦手なので、僕の興味は必然的にアートだとか音楽に限られてしまうのでこの後の話はその類となる。

ちなみにその話をする前に、食べ物についての印象を書いておくと、これもやはり想像していたとおり、海産物と野菜がほとんどない。要は肉。とにかくハムやソーセージの種類が多く、あとはチーズ、パン。
最近、野菜中心の食生活に変わってきたので、これはけっこうしんどかった。オリーブオイルをかけたタコとか新鮮な葉野菜なんかが無性に食べたかったが、残念ながら皆無に近い(もちろんきちんと探せばあると思うけど)。
そして知らなかったが白ワインがとてもおいしい。地元ならではの品種、そしてリースリングやシャルドネなど、とても種類が多く、どれも甘くなくすっきりとしていて好みの味だった。日本で今ひとつ知られていないのはオーストリアワインのほとんどが国内消費向けに作られているからだそうだ。実にもったいないなあと思う。

ということで、ここから僕の好みの話。
ウィーンの芸術というと、大体想起されるのがグスタフクリムト、エコンシーレ。なんとなく知ってる、という程度だけど、僕らがよく知っている印象派などのムーブメントより少し後。とはいえモダンという感じでもないので、美術史的にはちょっとマイナーかもしれない。
表現主義とも言われるらしいが、それもなんとなくピンとこない。美術史的にまとめなくちゃいけないのでそういう風になった、というだけで、取り立てて独自のムーブメントがあった、という風に僕は感じなかった。
クリムトというと大体あの金ぱくのちょっとエロティックな感じの絵がイメージされると思うが、ああいうのはほんの一部で、元々のプロフィールは作家と言うより装飾家、なおかつ古典主義の教育をきちんと受けた人なので、日本でのイメージと少し違う。
美術館や劇場などの装飾の仕事が多かったらしく、依頼主も行政や大学などがメインだったようなので普通に「建築に携わる職人」というイメージだったのかもしれない。ただ、風景画もたくさん描いていたようで、独特の線と構図で不思議な印象を与える。僕はこれらがとても気に入った。

エゴンシーレは奇妙な線の人物画で有名だが、クリムトと比べるとアーティストという感じで、他のいろいろな作家の影響を受けているように感じられた。上手いというよりはセンスのある絵で、若くて夭逝したことから、天才と言われているらしい。彼も風景画を残しており、クリムトと同じく面白い構図やタッチなのが印象的だった。
なお、クリムトの作品はウィーンのいろいろな場所で見ることができるが、センスがよく、現代的な展示の「レオポルドミュージアム」をお奨めしたい。人も少なく、じっくり鑑賞できる。
美術館ではもうひとつ印象的だったのは美術史美術館。
歴代ハプスブルク家の君主が買い集めたコレクションが所狭しと並ぶ美術館で、そういう意味で美術館というよりは家の収蔵品を特別にお見せします、という感じ。なので美術館としてのテーマ性というよりも、その時々の君主の趣味が左右されるので、必然的にジャンルに偏りがある。
想像されるようにやたらとお金持ちの方々の肖像画があるのだけれど(本当に辟易するくらいある)、特筆すべきは意外にもブリューゲルの絵がけっこうあることだ。

僕はブリューゲルがけっこう好きで、昔、ブリュッセルの王立美術館で見たことがあったが、ここにはかなりの著名な作品が置いてある。バベルの塔を始め、農村の暮らしを描いた一連の作品、そして僕が好きな雪中の狩人などもあり、かなり見応えがあった。
なぜ君主がブリューゲルなどに興味を持ったのかよく分からないが、恐らく諸外国の庶民の暮らしの資料としてではなかったんじゃないだろうかと思ったりした。
ちなみに日本人の好きなフェルメールの作品も一点、すごく普通に(無造作に)置いてある。ブリューゲルもそうだけど、どちらかというとハプスブルク家の人たちはこの手の絵はあまり興味がないように見える。

そして音楽。これについては音楽の都と言われるだけあって、ウィーンと関わりのある音楽家はとても多い。恐らく僕たちの知っている音楽家のほとんどが少なからずウィーンと関係している。なかでも著名なのはやはりモーツァルトだろうか。ウィーンのいたるところに彼の自画像があり、土産店ではそれをパッケージに使ったお菓子が売られている。
ただ、モーツァルトはザルツブルクの出身で、ウィーンに引っ越したのは25歳、その後35歳で亡くなっているのでウィーンでの活動はたった10年。なので「ウィーンの音楽家」というと少し違うかもしれない。
せっかくなのでモーツァルトを聴きに行った。とは言ってもきちんとしたコンサートではなく、観光用のバージョン。「ウィーンモーツァルトオーケストラ」という楽団らしく、当時の貴族のファッションで代表曲をちょこっとだけ演奏してくれる。
とはいえオーケストラのコンサートをきちんと聴いたことがあまりないので、なかなか楽しめた。トルコ行進曲なんてとても優雅な曲だと思っていたけど非常にドライブする楽曲だなあとか、魔笛の有名なソプラノの旋律はかなりめちゃくちゃなメロディラインだなあとか。そしてなぜかこっそりシュトラウスの楽曲を混ぜるあたりが商売上手だなあとか。
でも僕はあまりモーツァルトは好みではない。
元々宮廷からの依頼曲をこなしていた人だから、どうしてもそういう人たちが好みそうな曲になっているし、長調が多く、装飾的な音が僕には過剰に感じられる。そんな評価軸はいらないと思うが、「ミニマル」という視点からはほど遠い。

同じウィーンの作家としてはシューベルトが好みで、学生時代からシンプルな歌曲をよく聴いていた。メロディが情緒的で親しみやすかったのもあったかもしれない。「白鳥の歌」の中からの「セレナード」などは当時、ロックバンドしか出演していなかったステージで無理矢理演奏したこともある。
ウィーンに生家があると言うことで出かけてみた。
集合住宅のような建物で、18世紀当時は16家族が住んでおり、その中の一室がシューベルトの生家である。たかだか十数畳程度の一室で、そこに家族全員で住んでいたらしい。先生だったお父さんが教育熱心だったらしく、音楽の才能を伸ばしたとのことである。
生家はつましい博物館となっており、愛用のメガネやピアノ、家族の肖像画などが飾られている。決して裕福な生活ではなかったと思うが、なんとなく暖かく、ほっこりした気分になれる。とても不思議な空間だった。

ということで、もちろん行ったところは他にもたくさんあるのだけど、この辺で。
当たり前だけどこの歳で改めて美術、音楽という両面できちんとヨーロッパに触れ合えたのはとても良かったと思う。昔なら文化における知識のone of themと感じるところなんだろうけれど、今はひとつひとつが染み渡る感じがする。
そういうことが歳を取って良かったことのひとつなのかな、と思ったりした。いいのか悪いのか、僕にはよく分からないけれど。


















![イントゥ・ザ・ワイルド [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51nAvVnDkNL.jpg)